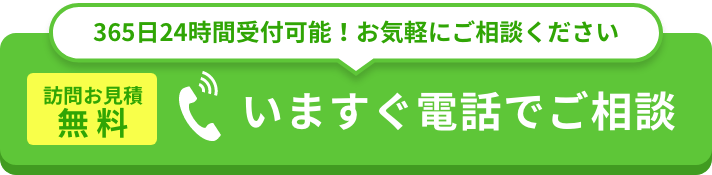お葬式に給付金?知っておきたい制度や受給条件
2022/01/21

家族が亡くなったとき、遺族として気になるのが「お葬式のお金」ではないでしょうか。
規模に関わらず、葬儀を行う以上まとまったお金が必要となるのが事実。資金に余裕がない方にとって、お葬式のお金は痛い出費となってしまうものです。
そういった方に知っていただきたいのが「お葬式に関する給付金」です。実は、故人が加入していた保険の種類によっては、給付金を受けられる場合があります。
今回はお葬式の費用を軽減するための「給付金」について詳しく解説します。
目次
お葬式で受け取れる「給付金」がある
冒頭でも触れた通り、お葬式を行うにあたり利用できる給付金が存在します。全員が受給できるわけではないものの、一定の条件を満たすことで給付金を受け取ることができるのです。
そのうえ、給付額も3万~7万円と高額である点が魅力。お葬式を行うのであれば、給付金について正しく理解しておかないと損をしてしまう可能性があります。
ちなみに、お葬式で給付金を受給できるのは、故人が「国民保険加入者」もしくは「社会保険加入者」のいずれかであった場合です。故人が上記の保険に加入していた場合は、忘れずに給付金の申請を行ってください。
故人が国民保険加入者であった場合
故人が国民保険加入者であった場合、いくら受給できるのか、どのように申請するのかを正しく理解しておく必要があります。単純に「故人が加入者であった」というだけでは給付金を受給することはできません。
正しい支給額を確認したうえで申請しないと、せっかくの給付金のチャンスを逃すことになってしまいます。
故人が国民保険加入者である場合には、以下を参考にしてください。
支給額
故人が国民保険加入者である場合、給付金の支給額は自治体によって金額は異なるものの、3万~7万円です。
給付金の金額における差は、年収や所得などによるものではなく、自治体ごとに設定している価格が異なることが理由。お住いの住所により、給付金として受け取れる金額は異なるため一概にはいえません。
申請方法
故人が国民保険の加入者である場合には、各市区町村の役所に申請を行います。
必要書類を揃えたうえで申請を行う必要があるため、事前準備をきちんと済ませることが大切です。
なお、故人が国民保険加入者で給付金を申請する場合には、以下のものを準備する必要があります。
・国民健康保険証(故人のもの)
・お葬式の領収証
・申請者の印鑑
・給付金の振込先の口座番号
上記全てが揃っていないと給付金の申請手続きを進めることができません。
なお、申請者の印鑑については、主に喪主を務める方のものが一般的です。明確な規定はありませんが、誰の印鑑を使用すべきか迷ったときには、喪主を前提に検討してみてください。
申請における注意点
お葬式の申請を行うにあたり、注意したいのが申請期間です。死亡した日から2年以内に申請しなければなりません。仮に申請期間を過ぎてしまうと、給付金の申請ができなくなるため注意しましょう。
故人が社会保険加入者であった場合
故人が社会保険加入者であった場合と、国民保険加入者であった場合とでは、支給額や申請方法が大きく異なります。加入保険を明確にしたうえで、正しい方法で申請しなければなりません。
ここからは、故人が社会保険加入者であった場合の支給額や申請方法、注意点などを解説していきます。
支給額
故人が社会保険加入者であった場合の給付金は、一律5万円が支給されます。前項で触れた国民保険のケースとは異なり、地域によって支給される制度ではないからです。
「埋葬費」として、全てのケースで5万円が支給されるのが社会保険の特徴。想定していたよりも少なかった、と慌てることはありません。
ただし、健康保険組合によっては、独自の補助金制度を設けている場合があります。その場合は、支給額が上記とは異なる場合があるため、きちんと健康保険組合に確認をとることが大切です。
申請方法
お葬式の給付金を受給するにあたり、故人の加入保険が「社会保険」であった場合には、勤務先(もしくは所轄の社会保険事務所)に給付金を申請します。
なお、申請するにあたり、必要なものは以下の通りです。
・死亡診断書(もしくは埋葬許可証)
・勤務先事業主による証明書類
・故人の健康保険証
・申請者の印鑑
国民健康保険同様、不足があると申請ができないため注意をしましょう。
また、「勤務先事業主による証明書類」には、記入項目があるため適宜必要情報を記入し、捺印も行ってください。
申請における注意点
お葬式の給付金を受ける際には、故人の死亡後2年以内に申請する必要があります。期限を過ぎてしまうと、申請しても無効となってしまう恐れがあるため注意してください。
おわりに
遺族にとって、お葬式の費用は大きな負担になりやすいものです。少しでも、金銭的な負担を軽減したいというのが本音ではないでしょうか。
今回は、「国民健康保険加入者」「社会保険加入者」のいずれかであった場合に活用できる給付金について解説しました。
まずは、故人が加入していた保険内容を確認し、希望する場合は申請手続きを行ってください。
監修者:大坂 良太 所有資格:遺品整理士・事件現場特殊清掃士
作業は”丁寧”がモットー。大切な人が遺したものだから、私たちも 大切に扱わせていただきます。遺品にまつわる思い出話をうかがいながら、 一つずつ整理していく。こうした遺品整理の過程が「思い出の整理」となり、 少しでもお客様の心が温かくなればと願っています。

対応エリア全国に拡大!
まちの遺品整理屋さん全国エリア、出張無料で訪問お見積り!
24時間365日ご相談・お問合せいただけます。まずはお気軽にご連絡ください。
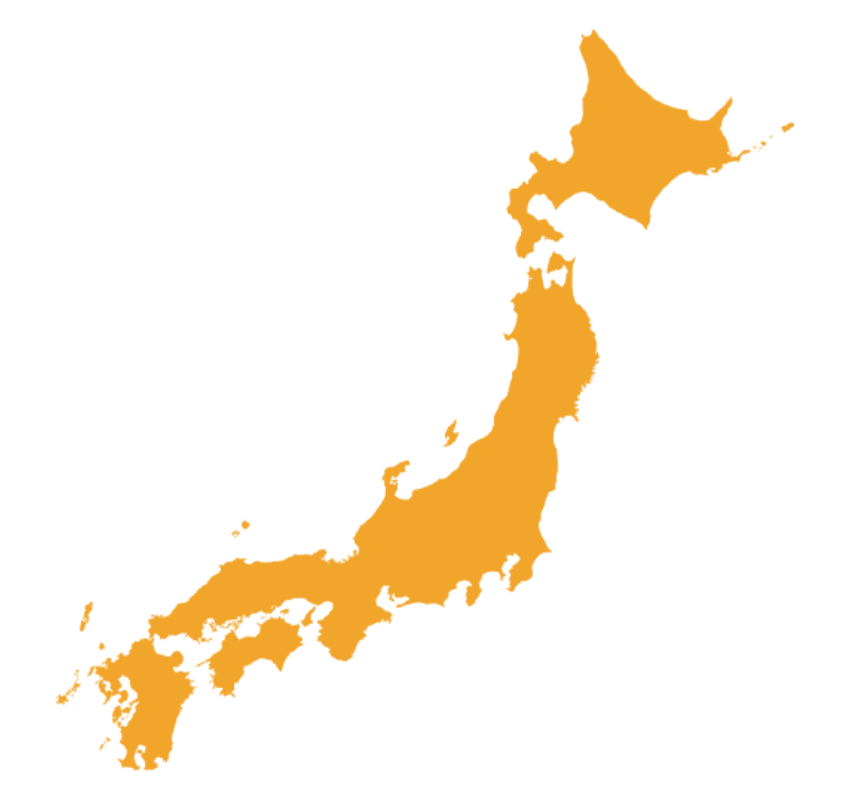 ※山間部等、一部お伺い出来ない地区がございます。
※山間部等、一部お伺い出来ない地区がございます。
お気軽にお問い合わせくださいませ。