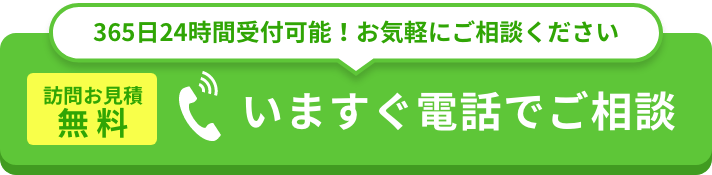火葬許可申請書ってなに?提出方法や火葬の流れについて
2021/07/16
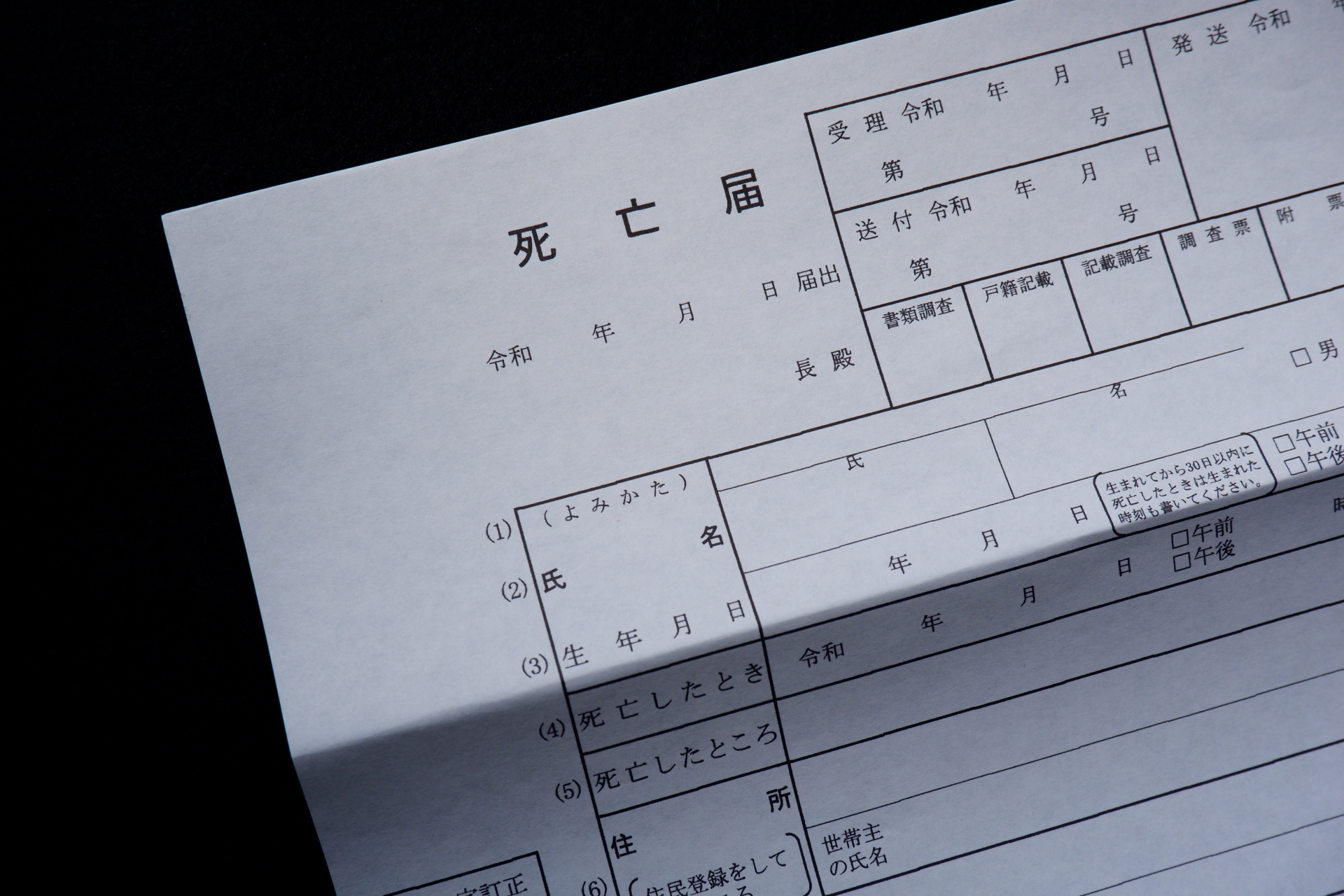
故人が亡くなった後、提出が必須となる「火葬許可申請書」。身近な人が亡くなったのが初めてであれば、どのような書類なのか、そもそも提出は必要なのか、などさまざまな疑問が生じてしまうもの。
しかし、とても大切な書類ですので「不備」「提出忘れ」があってはいけません。火葬許可申請書について正しく理解し、きちんと提出する必要があります。
そこで、今回は火葬許可申請書の概要や提出方法などについて、幅広くご紹介します。
目次
火葬許可申請書とは?
火葬許可申請書とは、文字通り火葬の許可を得るための申請書です。
火葬するためには、市区町村から「火葬許可証」と呼ばれる書類を受け取らなければなりません。遺族が独断で火葬場に連絡し、火葬を行うことはできないのです。
火葬許可証を受け取るためには、火葬許可申請書に必要項目を記入して市区町村に提出する必要があります。
火葬許可申請書に不備などがなければ、その場で受理され、すぐに火葬許可証が発行されます。
火葬許可申請書の提出方法
ここからは、火葬許可申請書を提出する方法についてご紹介します。入手方法から、提出先、提出する人などについて触れていきますので、初めての提出に悩んでいる方は参考にしてみてください。
窓口で受け取る
火葬許可申請書は、市区町村役所の窓口に設置されているか、窓口の担当者に声をかけて取得します。
持ち帰って自宅で記入してから提出することもできますが、受け取ったその場で記入して提出することも可能です。
一般的には、死亡届を提出するタイミングで、同時に火葬許可申請書を提出することが多いです。
ただし、市区町村役場によっては、火葬許可申請書が不要な場合もありますので、不安な方は一度窓口に問い合わせておきましょう。
親族もしくは同居人が提出
火葬許可申請書を提出するのは、故人の親族もしくは同居人です。
基本的には、配偶者や子ども、兄弟などが提出するケースが多い傾向にあります。ただし、火葬許可申請書を提出するのは、死亡届を提出した人と同じ人物でなければなりません。
そのため、前項でも触れた通り死亡届を提出するタイミングで、火葬許可申請書を提出することをおすすめします。
故人の住所がある市区町村へ提出
火葬許可申請書は、故人の住所がある市区町村へ提出してください。住民票、もしくは本籍などを確認し、提出先を調べましょう。
また、火葬許可申請書が受理された後に受け取る「火葬許可証」は、うっかり紛失しないように注意してください。火葬許可証は、火葬場に提出しなければなりませんので、紛失してしまうと、スムーズに手続きが進みません。
実際、故人が亡くなった後は、遺族が慌ただしくなってしまうことが多く、「どこに置いただろう」と紛失する場合が多いです。
故人の貴重品とセットにしておくなど、必ずわかる場所に保管しておきましょう。
提出期限は国内外で異なるため注意
火葬許可申請書の提出期限は、国内と国外とで異なりますので注意してください。
国内で死亡した場合は、死亡後7日までとされています。ただし、死亡した日が不明確である場合には、「死亡を知った日」から換算して7日で問題ありません。
また、7日目が土日や祝日など、休日である場合には、よく平日まで提出期限が延長されます。
一方、国外で死亡した場合には、死亡した日(もしくは死亡を知った日)から、3か月以内に提出します。
旅行や仕事などで海外に訪れている最中に死亡した場合は、提出期限に余裕があります。
火葬許可証を受け取ってから火葬まで
火葬許可証を受け取ったものの、どのように火葬まで進むのか疑問を感じる方は多いです。
ここからは、火葬許可証の提出から火葬まで、どのような流れで進んでいくのかを見ていきましょう。
火葬許可証を火葬場へ提出する
市区町村役場で受け取った火葬許可証は、火葬場の管理事務所へ提出する義務があります。
火葬を行うためには、市区町村で発行された火葬許可証が必須。うっかり忘れてしまうと、火葬できませんので注意してください。
なお、提出日は火葬当日ですので、きちんと準備しておきましょう。
火葬後に埋葬許可証を提出する
火葬が終了したら、火葬場から埋葬許可証を受け取ります。
埋葬許可証とは、遺骨を埋葬するためにも必要な書類です。お墓などへ納骨・埋葬する場合は、埋葬許可証がなければ受け付けてもらえません。
「火葬して終わり」ではありませんので、火葬後の対応にも注意してください。
おわりに
本ページでは、火葬許可申請書についてご紹介しました。
火葬を行うためには、市区町村に火葬許可申請書を受理してもらわなければなりません。また、市区町村で発行する火葬許可証の取り扱いにも十分気をつけることが大切です。
故人の火葬を控えている方は、火葬許可申請書について理解を深め、スムーズに進行できるように準備しましょう。
監修者:大坂 良太 所有資格:遺品整理士・事件現場特殊清掃士
作業は”丁寧”がモットー。大切な人が遺したものだから、私たちも 大切に扱わせていただきます。遺品にまつわる思い出話をうかがいながら、 一つずつ整理していく。こうした遺品整理の過程が「思い出の整理」となり、 少しでもお客様の心が温かくなればと願っています。

対応エリア全国に拡大!
まちの遺品整理屋さん全国エリア、出張無料で訪問お見積り!
24時間365日ご相談・お問合せいただけます。まずはお気軽にご連絡ください。
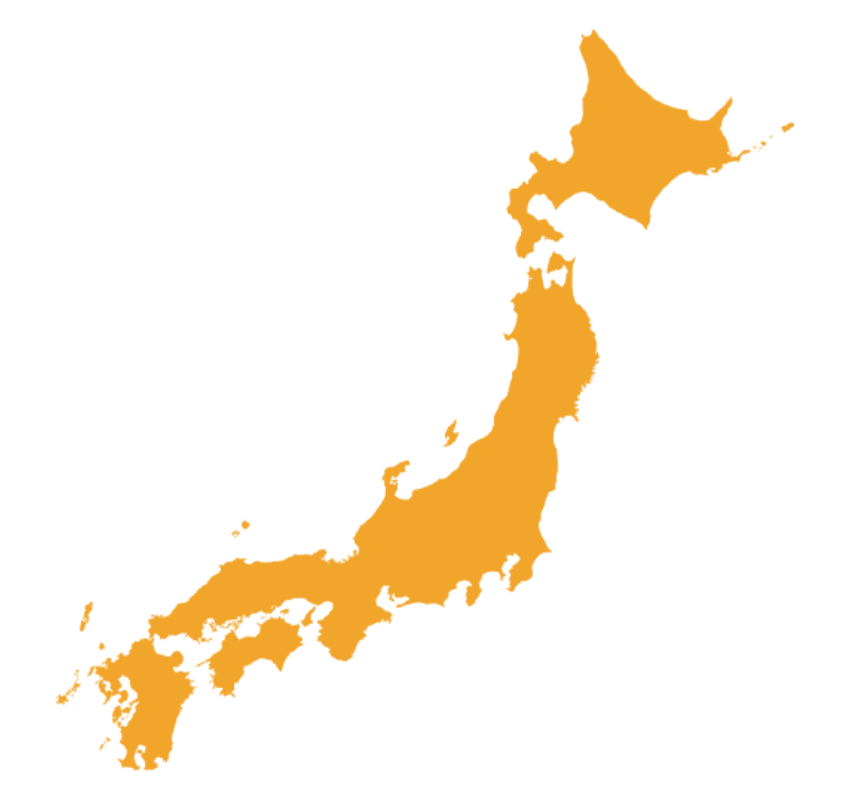 ※山間部等、一部お伺い出来ない地区がございます。
※山間部等、一部お伺い出来ない地区がございます。
お気軽にお問い合わせくださいませ。